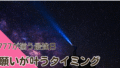半夏生(はんげしょう)
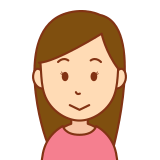
やぁちゃま
「半夏生(はんげしょう)」という言葉を聞いたことはありますか?
昔の「二十四節気」と「雑節(ざっせつ)」と呼ばれる暦のひとつ。
日本の暦って意外と知らない言葉がありますね💦
半夏生っていつ?
半夏生は、夏至から数えて11日目の7月2日ごろから約5日間を指します(※年によって1日前後ズレます)。
2025年は7月1日。
田植えが終わる頃とされていて、農作業と深く関わってきました。
一年の折り返しでもあり、
田植えを終える目安の日で
無事に終えたことへの感謝や収穫の予祝を行う日になります。
名前の由来は?
「半夏生」という名前、ちょっと不思議ですよね。
実はこれ、薬草の「半夏(はんげ)」という植物が生える頃を意味しています。
また、「半夏生草(はんげしょうそう)」という植物もあります。
白い葉が特徴的で、まるで半分だけ化粧をしたように見えることから名付けられました。
半夏生の風習
日本各地には、半夏生にまつわるいろいろな風習があるそうなんです。
- 関西地方ではタコを食べる習慣があります。
田植えを終えた後、タコの足のように稲がしっかり根を張るよう願いを込めて食べるのだとか。 - 農作業を休む日ともされ、
- 「この日を過ぎて田植えをすると稲の育ちが悪い」と言われてきました。
- 半夏生に雨が降ると大雨になるなど、
- 天気にまつわる言い伝えも残っています。
このころの大雨を「半夏雨(はんげあめ)」
その時の洪水を「半夏水(はんげみず)」と呼んでいます。
最後に
半夏生を過ぎる頃は例年ならば梅雨の最盛期。
災害につながるような雨の降り方をするところもあります。
季節の移り変わりをより適確につかむために設けられた
特別な暦日である雑節のひとつである半夏生
あまり知られていないですがお米を作るときにはとても大事な日なんですね。
最後まで読んでくださりありがとうございます。